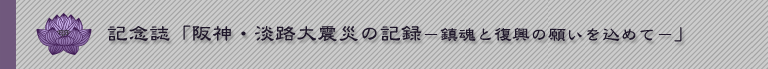|
|
||||
| 13章 『あの日』を忘れない |
小林 文雄 |
|
||
○ [生死をさ迷う] ロビーは20〜30メートル四方500平方メートル余の広さにもう余裕はない程であった。 空いたところに下ろされ、重傷の様子だから早い処置をしてあげて下さいと看護婦に言い残し、救助隊の人は次の救助に出かけた。 医師が私を検診する迄、10分位の時間はかかったのではないかと思う。 それは想像するに及ばず突発の大地震、押しかけ、また搬送された負傷者と重傷者、当直の医者、看護婦ではどう対処するも限界がある。 その僅かの時間にも次々と怪我人が運び込まれる。すぐ近くで親の遺体につかまり、親の名前を呼び叫ぶ子供達を目にし、自分の今あるこの命の有り難さを感謝した。 医師が私に巡って来た。名前も住所も全く聴かない。それはこの状況から当然と思われた。先生から「打撲か、骨折か」ときかれた。私は「頭は幸い怪我はありません。両腕も動きます」医師は頭と両腕を動かし「ウン良かった、良かった」と言ってくれ、次ぎに下半身の診察になった。パジャマを着たままである。医者が腰に手を当て看護婦が体を起こそうと先生の指示で動作した。 その瞬間、大きな悲鳴、それはどんな声が出たか自分でも解らない。脂汗と涙が一挙に吹き出た。 先生いわく……「これは骨折や……、骨折ぐらいで命は落とさへん。大丈夫や、ヨシッ頑張れよ……」。看護婦さんに「この患者さん、診察室前の横の方に寝かしてあげといて……この言葉を残し、次々と負傷者の対応に当たられた。 診察室が1〜6号室ほどあった。私は奥まった6号室の前へ、患者さんが診療前に待ち合うビニルレザーの3人掛位の椅子の上に寝かしてくれた。 丁度壁に椅子を寄せてあることから、体を壁につけ落ちることが避けられた。毛布に巻かれ両足を伸ばすだけの椅子の長さが無く、ヒザを立てたままで、治療の時をまった。 この間も余震が絶え間ない、体感の3〜4の震動は何回もあり、その都度病院内の恐怖の悲鳴は忘れられない。 診察室の各部屋は満員で、1つのベッドに何人もが先生の治療を受けている様子である。一方、廊下では足の踏み場もない状況に、怪我人達が横になり座ったままで先生の手当を待っている。 私は診療室の近くであるから、医師や看護婦の交わすことばや診察室の携帯ラジオから流れる地震情報も耳にすることが出来た。 時間はもう正午であろうか。しかし快晴であった神戸の空が、今は夕立の来る空模様の暗さで、病院も薄暗い。
そうだ「電気は灯かない。水は出ない。電話は全く通じない」医師看護婦の外部への要請も全くとざされ在庫医薬品にも不足を来していた。 ロビーの向こうの方で『救援の差し入れが届きました。数が少ないので皆にあたる様にパンかおむすびをどちらか一ケを取って下さい』 朝から一口の食事もとっていない人達、それはアッという間に無くなり奥のこちらの方にはとうてい届かない有様で仕方がない。次ぎに届けられるのを待たざるを得ない。 ラジオで、「長田区市立西市民病院の5階建ての建物が押し崩れている。灘区の火災の延焼、長田区の火災と倒壊している街並の情報である」如何に大きな被災であるかが窺える。医師看護婦の交わす言葉も沈痛のきわみである。 |
|||
|
|